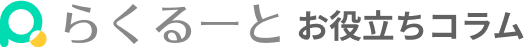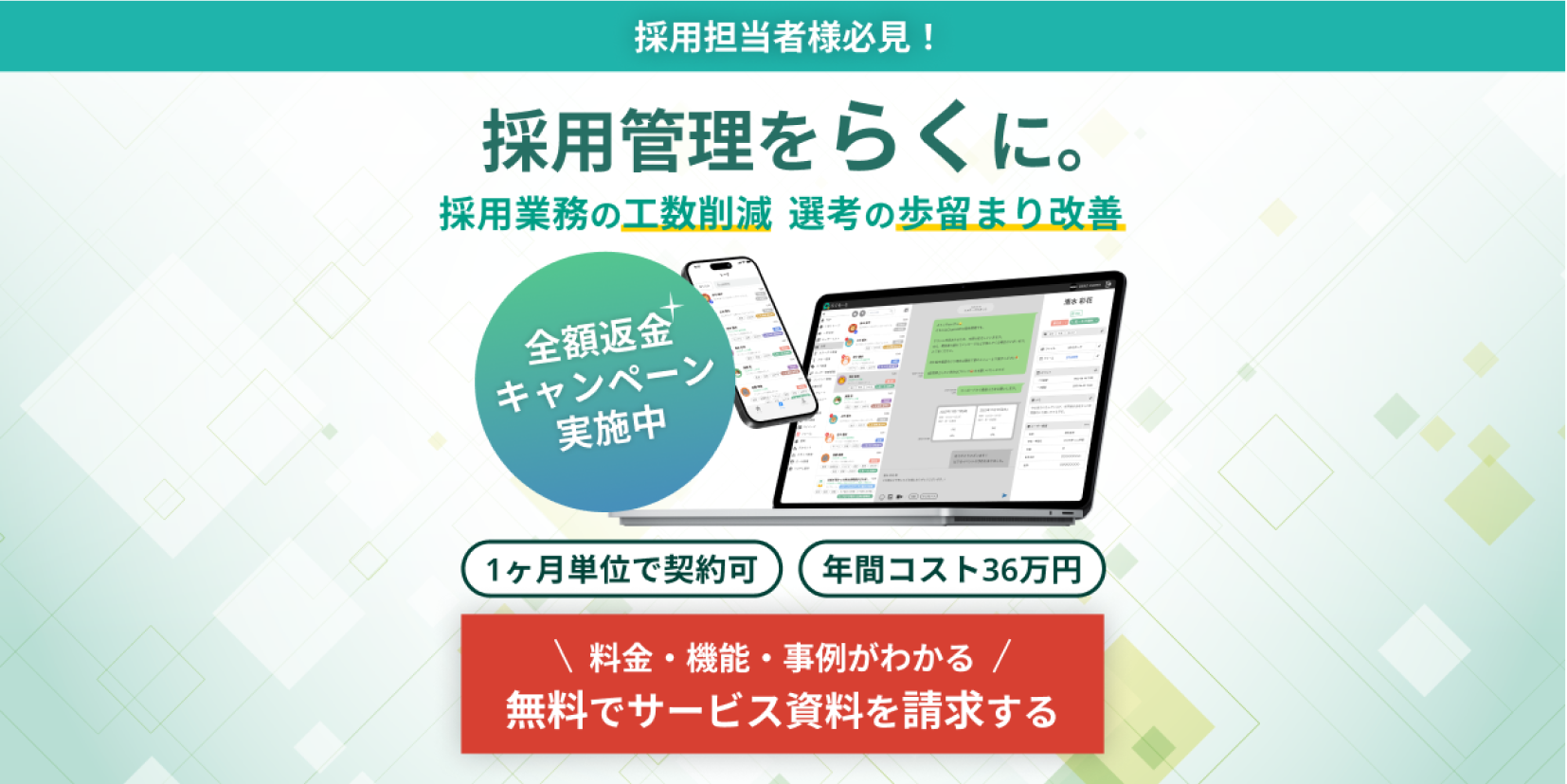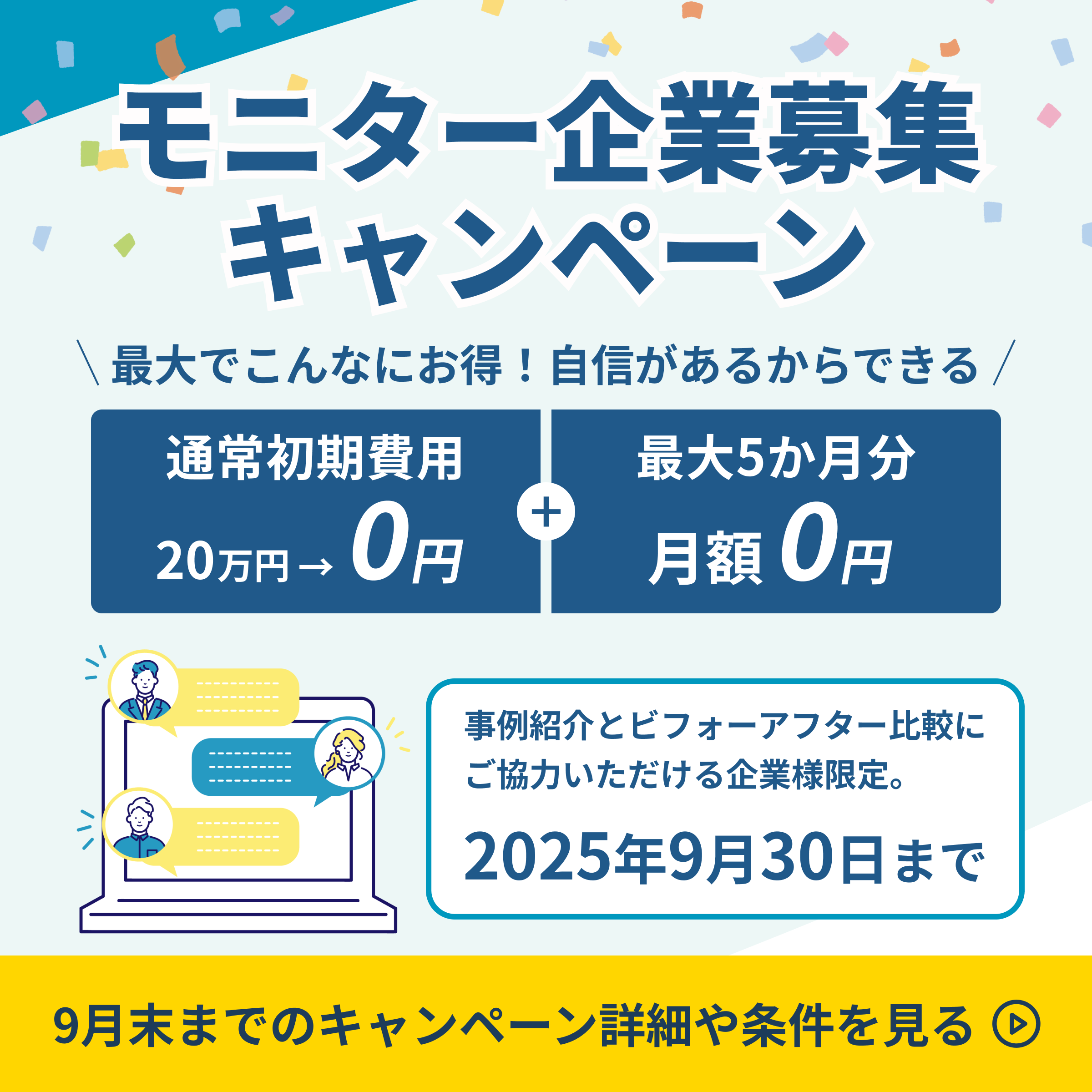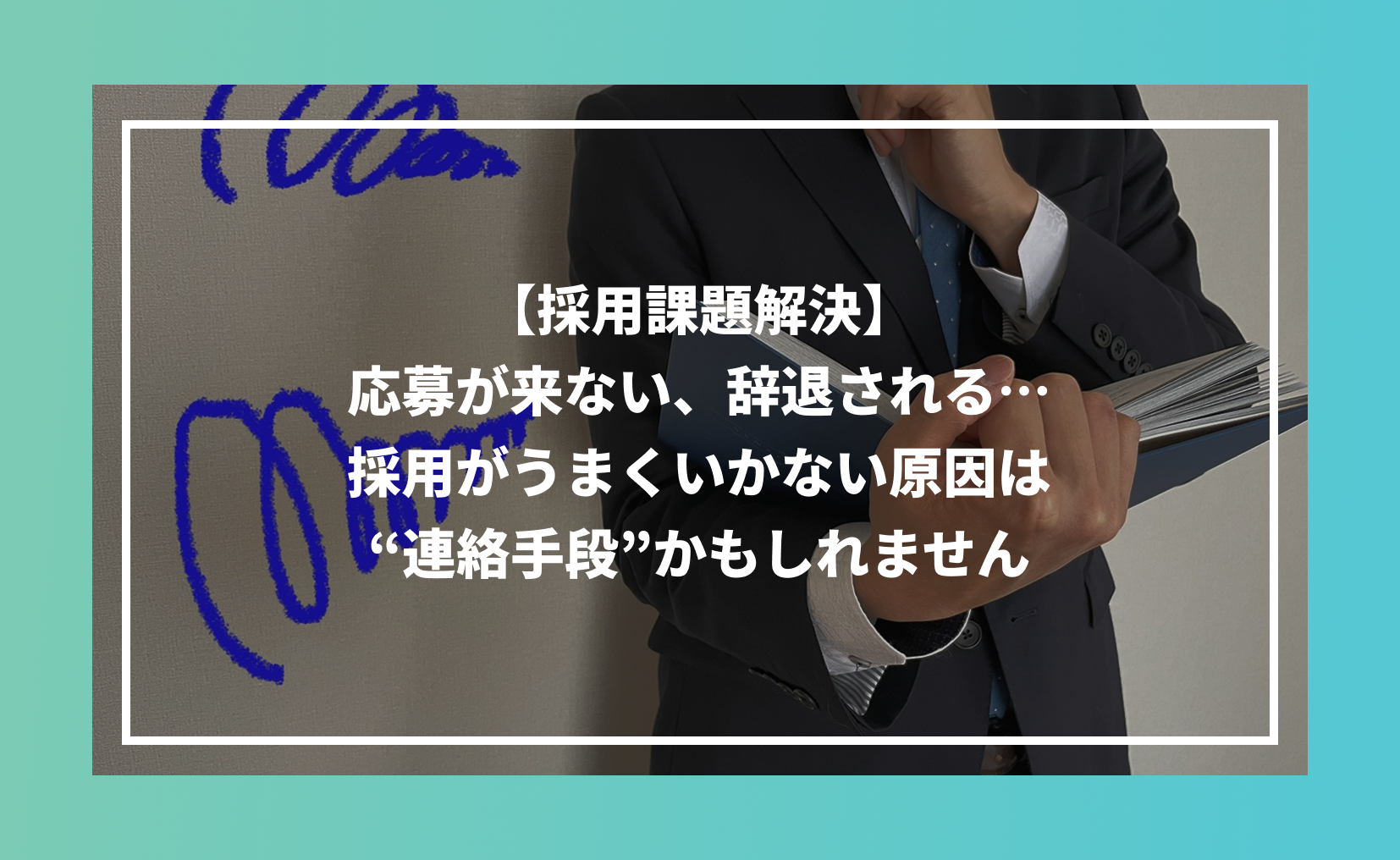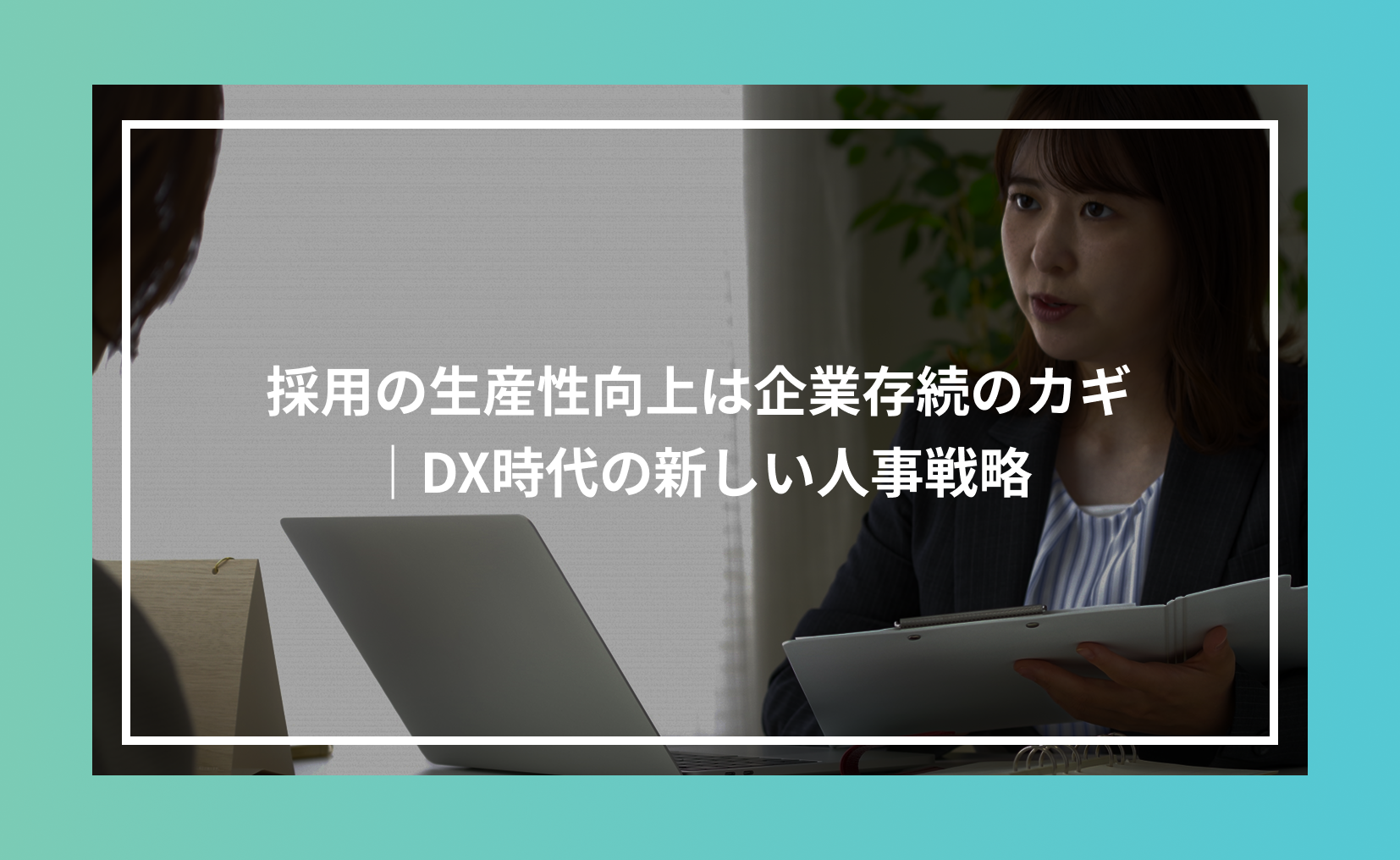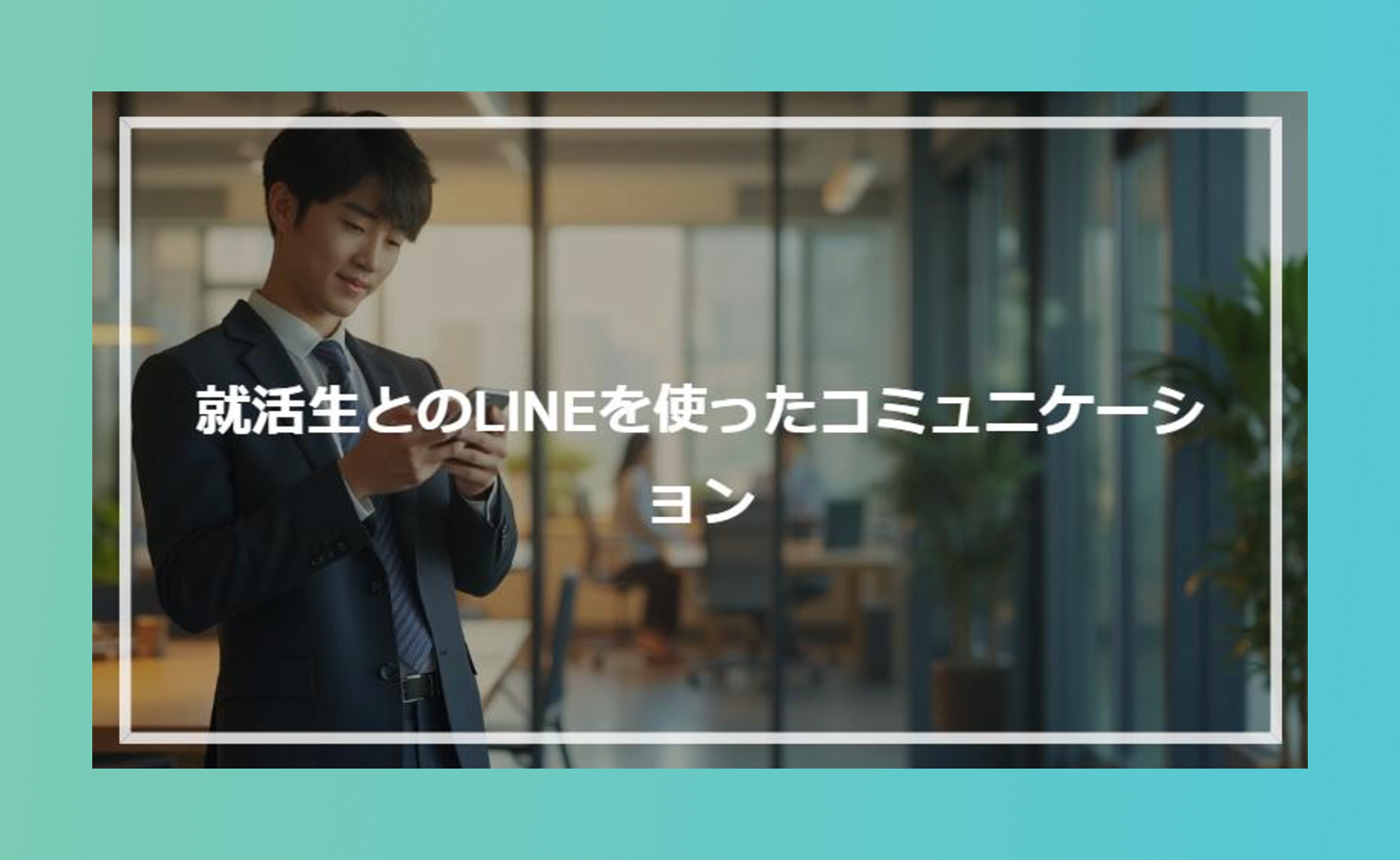1.スクラッチ開発に潜む落とし穴

1-1.魅力と現実のギャップ
「自社専用の採用システムをゼロから開発すれば、完全にフィットする仕組みが手に入るのではないか?」。そう考える企業は少なくありません。スクラッチ開発の最大の魅力は、要件に合わせて自由に設計できる点です。しかし現実は甘くありません。
①莫大なコスト
開発には数千万〜数億円単位の費用がかかる場合もあります。特に採用管理システムは機能が多岐にわたり、要件定義・設計段階から膨大なリソースを要します。
技術者一人あたり単価は高くなる一方です。技術者を何十人も使って開発できる企業は限られます。
一人あたりの開発できる生産性は限られ、品質を保つためのテスト工数はかなりかかります。
②長期の開発期間
要件定義からリリースまで1年以上かかるケースも珍しくありません。その間に採用市場は大きく変わり、完成時には「もう古い」仕組みになることもあります。
私の知り合いに、公的補助を受けながらシステムをスクラッチ開発した企業さんがいます。
営業力のある社長さんでしたが、結果はリリースが9か月の遅延。理由は要件定義にありました。
システム開発に携わったことのない方がシステム要件を伝える難しさを表しています。
③保守・運用負担
完成した後もメンテナンスが必要です。法改正や採用フローの変更、セキュリティ対策など、常に改修コストがかかります。
常時、技術者を保つには多くの工数を要します。
少しの機能変更で思わぬ工数がかかることが現実には多く存在します。
④市場変化への遅れ
採用市場は急速に変化しています。例えば「通年採用」「オンライン選考」「LINEを活用した候補者コミュニケーション」など、新しい動きが次々に登場します。スクラッチ開発では、こうした変化に即応するのが困難です。
また、技術も日々進化するため、数年単位でシステムを見直す必要があります。
1-2.事例に見る
システム開発の新規顧客開拓の営業をしていた際に驚いたのは、ユーザーさんが考えるコストの差です。
日常的にシステム開発を依頼している大手企業と違い、中堅・中小企業でシステム開発の発注に慣れていない方々が考えるコストは現実とのギャップが大きい。
私たちが見積もるシステム開発の半額くらいしかかからないだろうと思われていたり、時には桁が違っていることもあります。
IT=簡単に開発できる、というわけではないのが現状です。
採用DXにおいて、スピードと柔軟性は欠かせません。スクラッチ開発は理想的に見えても、現実的にはリスクが大きい選択肢なのです。
2.SaaS(クラウドサービス)とは? 採用DXとの親和性

2-1.SaaSの定義と仕組み
SaaS(Software as a Service)とは、ソフトウェア(アプリ)をインターネット経由で利用できるサービス形態です。ユーザーは自社でサーバーを購入したりアプリをインストールしたりする必要がなく、Webブラウザにアクセスすればすぐに利用できます。
従来のオンプレミス型(社内導入型)と比較すると、以下の特徴があります。
導入の速さ:契約後すぐに利用開始できる
初期コストの低さ:月額課金で利用可能、初期投資を抑制
保守不要:アップデートやセキュリティ対応は提供事業者が担保
常に最新機能:市場の変化に合わせた改善が自動反映
スケーラブル:利用人数や機能を柔軟に増減できる
2-2.なぜこのようなことが実現できるのか?
私たちシステム開発会社の目線で言えば、
「同じシステムを広く多くのユーザーに提供しているから」です。
スクラッチ開発は、個社固有のシステムを作りますが、クラウドサービスの形態ではシステムが共通です。
1億かかるシステムを作ったとして、スクラッチ開発ではそのままコストに1億かかります。
しかしクラウドサービスでいうと、例えば採用管理ツールのらくるーとでは、月5万円で提供しています。
そして今後も将来的に開発コストをかけていくので、とてもリッチなシステムを安く提供できるという利点が
クラウドサービスにはあるのです。
サービス提供者側はユーザーが増えるほどにコストを売上に変換できるため継続できるのです。
便利な機能を低料金、定額で使えるといったことは、クラウドサービスならではです。
事例にあげた、中堅・中小企業へのDX、採用管理ツールなどの解決策は、
クラウドサービスにこそあると私は強く思います。
2-3.SaaSの弱点
では、クラウドサービスの弱点とは何でしょうか?
特に見逃せない弱点は、個社対応を前提としていないことです。
スクラッチ開発なら、自社専用にゼロから設計できるため、独自の業務フローや特殊な呼称・手順をシステムにそのまま落とし込むことが可能です。しかしクラウドサービスは「多くの企業が共通して使えるように設計された仕組み」であるため、個別要望に応じたカスタマイズは限定的です。
その結果、利用企業側では次のような調整が必要になります。
・自社内でルールを変更する:システムに合わせてフローを整理し直す必要がある。
・固有の名称や使い方を覚える:サービスが提供する呼び方に慣れなければならない。
一見するとこれは「自社のやり方に合わせてくれない=不便」と映ります。特に長年の運用で定着したやり方がある場合、現場から抵抗が出ることもあるでしょう。
しかし、この弱点は見方を変えるとむしろチャンスでもあります。
クラウドサービスは業界標準の考え方を前提に設計されているため、システムの使い方に合わせて社内ルールを見直すことで、業界のベストプラクティスを自然に取り入れることができます。「なぜ今までこの手順を踏んでいたのか」といった無意識の“慣習”を棚卸しするきっかけにもなります。
システム導入のタイミングは、良くない習慣を変える絶好のチャンスです。例えば「候補者対応は担当者の個人メールで行う」といった属人的な慣行を改め、クラウド上で一元管理する文化へ移行することができます。これは単にシステムを使うこと以上に、組織全体の生産性と透明性を高める効果をもたらします。
まとめると、クラウドサービスの弱点は「個社対応をしていない」ことにあります。しかし、それは同時に業界標準の仕組みを積極的に活用し、自社の業務を進化させるチャンスでもあります。導入にあたっては「システムに自社を合わせる」のではなく、「システムを通じて業務を改善する」と捉えることが、SaaSを最大限に活かすポイントなのです。
2-4.採用活動における強み
採用活動は、母集団形成から歩留まり管理、内定辞退防止まで、プロセスが複雑です。SaaS型採用管理ツール(ATS)を導入することで、これらをクラウド上で一元管理できます。
候補者データの集約
各フェーズの歩留まり率を可視化
LINEやメールなど複数チャネルの統合
内定者フォローの自動化
マイナビキャリアリサーチLabの調査では、24年卒採用で内定辞退率が「3割以上」の企業は56.8%に達しました【脚注1】。
また26年卒学生の平均エントリー社数は28.5社と直近5年で最多水準です【脚注2】。
候補者が複数社を比較する今、レスポンスの速さと候補者体験が採用成果を大きく左右します。
こうした課題に対し、SaaSは導入スピードと柔軟性を兼ね備えており、採用DXの現実解となっています。
2-5.SaaSの柔軟性
SaaSの大きな利点は「合わなければやめられる」点です。スクラッチ開発は一度導入すると撤退が難しく、多額の sunk cost(埋没コスト)が発生します。SaaSは契約単位で切り替えが可能なため、まず試しに導入し、成果がなければ別のサービスに移行するという柔軟さがあります。
3. 導入事例から見えるSaaSの有効性

SaaSの良さは、導入のしやすさにあります。
弊社では、この2年間で8つのSaaSを導入しました。(勤怠システム、経費申請、会計、タレマネシステムなど)
三か月に一度のペースで新たなサービスを試したことになります。
これは一般的にハイペースではありますが、不可能ではありません。
弊社ではこの成果として、管理部6名体制から50%減の3名体制という生産性向上とコスト削減を実現することができました。
(このあたりのお話しは別の記事でまとめたいと思います)
この経験からわかったのは、スピード感をもって導入することが業務の成功にもつながるということです。
クラウドサービスの利点として運用性の高さ(インストールやバージョンアップ不要)に加え
サービス提供会社には、多くのユーザー企業を導入してる経験があるため、スムーズな導入が可能です。
弊社の採用管理ツールらくるーとでも、数多くの初心者向け導入資料や動画、ヒアリングシートや納得いただくまで行うリモートミーティングでお客様の課題解決に向けた設定を実施してます。
導入いただいた企業様に多くのお褒めの言葉をいただいております。
4.採用管理ツール「らくるーと」改善策の一例

採用DXを進める中で、特に注目されているのがLINEやSNSと連携できる採用管理ツール(ATS)です。
多くの学生や若手人材はメールよりも日常的にLINEを利用しており、連絡の即時性や心理的な距離感に大きな違いがあります。
既に就活生が企業との連絡手段において、就活ナビ、メールについで、3位にLINE(22%)を利用しています。
(調査方法:Freeasyによるインターネット調査 調査期間:2025年2月13日〜同年3月3日)
その代表的な例が、弊社が開発・提供する「らくるーと」です。
◆らくるーとの特徴
①LINE連携に特化
応募受付から説明会案内、面接日程調整、内定後のフォローまで、LINEを軸に候補者とコミュニケーションを一元管理できます。メールでは開封されずに埋もれてしまう連絡も、LINEなら高い開封率・返信率を実現します。
②歩留まり改善に寄与
選考途中で連絡が滞ると辞退につながりやすいですが、自動リマインド機能や一括配信機能により、抜け漏れなく候補者に情報を届けられます。結果として説明会参加率や面接出席率が向上し、最終的な採用歩留まりを改善します。
③内定辞退防止の仕組み
内定者に対するフォロー連絡も、グループチャットや定期的なメッセージ送信で効率化できます。候補者が「企業とのつながりを感じられる」状態を保つことで、安心感が生まれ、内定辞退の抑止につながります。
④業務負担の軽減
複数の担当者がやり取りをしても履歴がクラウド上で共有されるため、属人的な対応から脱却できます。煩雑なメール・Excel管理から解放され、人事部門が戦略業務に集中できる環境を整えます。
◆導入効果
・採用業務工数が1/2
・説明会参加から選考参加の選考率が20%アップ
・内定率が前年比157%
・内定承諾が率前年比195%
などのご報告をいただいております。
(上記はすべて導入事例に詳細をまとめています)
◆まとめ
「らくるーと」は単なるLINE連絡ツールではありません。
採用活動全体の歩留まりを改善し、内定辞退を防ぎ、母集団形成から内定承諾までの一連のプロセスを支える採用DX基盤です。
採用担当者の負担を軽減しつつ、候補者体験を高める仕組みとして、今後ますます必要とされる存在になってまいります。
5.まとめ:採用DXを前進させるために

スクラッチ開発は理想的に見えても、現実的にはコスト・時間・柔軟性の点で大きな課題があります。対して、SaaSはスピード導入でき、試行錯誤を許容する柔軟な仕組みであり、採用DXの現実解です。
改善策の一例として、LINE・SNS連携を強みにした「らくるーと」のような採用管理ツールを検討するのも有効でしょう。
採用DXを成功させる秘訣は「目的→設計→ツール選定」という順序を守ることです。目的を明確にしたうえで、最適なSaaSを選び、小さく始めて改善を重ねる。これこそが、採用の生産性向上を実現し、企業の未来を支える第一歩となります。
—
脚注(出典一覧)
マイナビキャリアリサーチLab「2024年卒 企業新卒内定状況調査」P57「内定辞退率」図表
マイナビキャリアリサーチLab「2026年卒 学生就職モニター調査(6月末)」トピックス「累計エントリー社数28.5社」